
江戸時代に初めて日本地図を作ったことで知られる伊能忠敬測量隊の一行が、熱海に合計で45泊していることが分かった。伊能忠敬の研究会(鈴木順子代表)は4日、起雲閣で創立20周年記念講演会を開き、渡辺一郎代表が講演し、忠敬の人間像や全国の測量を始めた経緯を紹介した。測量隊が最も多く宿泊したのは本土では岡山の64日が最高で、北九州、熱海、下田の順だったといい、「熱海には本土では3番目に多い45日宿泊し、地図の製作や温泉で旅の疲れを癒したと思われる」と研究の一端を披露した。熱海での宿泊が最も多かったのは伊豆半島を測量した第9次の測量で、熱海温泉に1カ月滞在したという。
座談会も開催され、忠敬の子孫や大学教授、斉藤栄市長らがパネリストを務めた。会員約40人が観測隊が1815年に宿泊した伊豆山温泉の「うみのホテル中田屋」に宿泊し、忠敬が率いた測量隊に思いをはせた。
◆第9次の測量1815年(文化12年)12月(旧暦)、忠敬は弟子11人とともに八丈島と伊豆七島を測量し、下田から伊豆東海岸を測量するの旅の中で熱海を訪れた。12月(旧暦)13日に網代、14日下多賀、15日、16日には熱海を測量し、それぞれ宿泊。17日に伊豆山に入り、18日から海岸沿いに小田原まで測量したのち、熱海に引き返し、熱海で年越しをするなど、約1カ月間滞在した。1801年にもにも熱海を訪れ、熱海本陣や網代、初島に宿泊している。
◆伊能忠敬(1745~1818年)江戸時代に全国各地を歩いて土地を観測し、日本初の実測による日本地図を作った人物。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
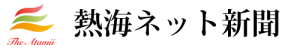























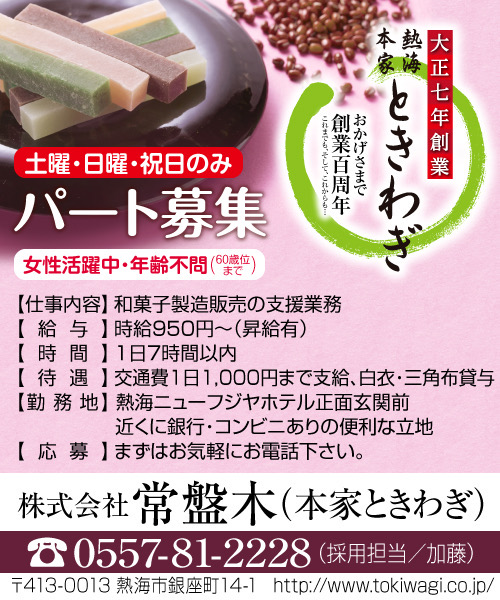
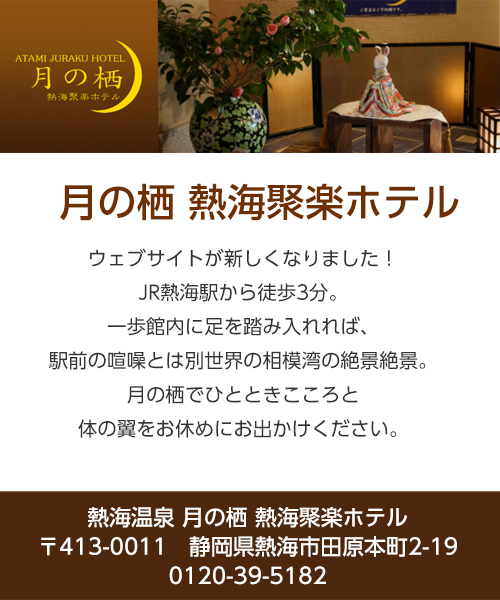
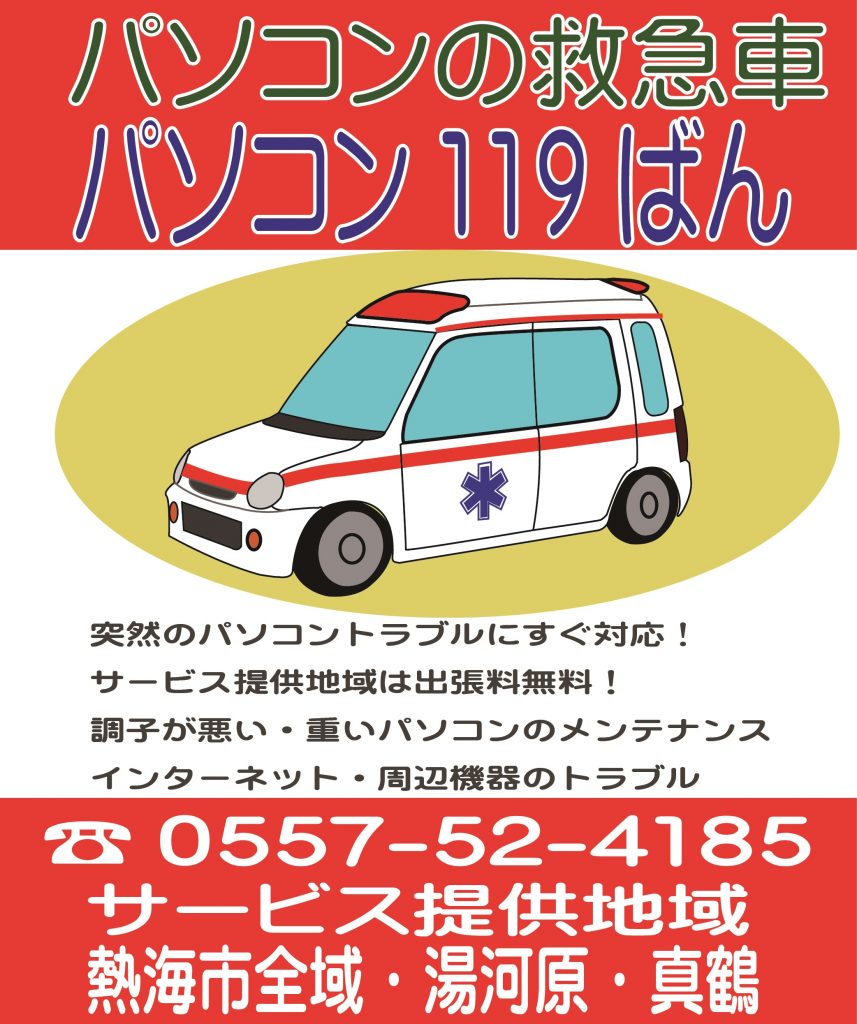
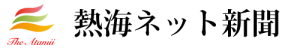
この記事へのコメントはありません。