
伊豆半島ジオパークのユネスコ世界認定を記念する講演会が6月13日、熱海市役所いきいきプラザで開かれた。伊豆半島ジオパーク推進協議会の専任研究員で地球環境学者の朝日克彦さんが「熱海で楽しむジオの魅力」と題して話し、北島鉄修会長をはじめ、ATAMIジオネットワークの会員40人などが熱心に耳を傾けた。
■ユネスコと日本のジオ感覚に違い
朝日さんは、これまで日本が行ってきたジオパーク活動とユネスコが考える活動には、違いがあり、考え方を変える必要があると強調。ユネスコが考えるジオパーク活動は「ジオロジー=地質学」ではなく、「持続可能な地域社会を実現するための活動。食べ物、観光、地場産品、文化、人々の暮らしすべてがジオであり、無理やり地質や石に結び付けて考える必要はない」と話した。
代表例として、2004年に最初に世界ジオパークに認定されたギリシアのレスボス島を挙げ、同島では1800万年前の森林の化石とともに、セーリングやハイキング、バードウォッチ、地場産品販売といったジオツーリズムに力を入れ、それに伴う女性の活躍がユネスコに高く評価されていると説明。
■なにもかも地質、石に結びつけるな
「世界的な地質遺産があることが前提だが、世界の人たちに伊豆半島に興味を持ってもらうには文化や芸術が意味を持つ。文学者たちが、どういう自然環境、歴史的な背景の中で名作を残したのか。温泉や食事とのかかわりは。そういったものを知ってもらうことをユネスコは期待している」と助言し、「入れ物(景観)の世界遺産と違い、ジオパーク活動はだれが何をするかが大事。中身が問われる。誘客や物を売るのに何でもジオロジーに結びつけるようなことをいつまでもやっていたら、世界認定のラベルがほしかっただけなのか、と認定を取り消されてしまう可能性がある。無形遺産(物語、伝説、神話、民謡、音楽)など地質以外の取り組みが重要」と警鐘を鳴らした。筆者も含め、会員の多くが「ジオ=地質学・研究科学」という潜在意識があり、朝日さんの話に目から鱗(うろこ)―。
■田畑朝恵さん、石川彰さんが講演
続いて前伊豆半島ジオガイド協会長の田畑朝恵さんが「伊豆半島のジオ旅」、ATAMIジオネットワークの石川彰さんが「ジオの視点で見る熱海」のテーマでそれぞれ講演した。ジオパークの奥は深い。
(熱海ネット新聞・松本洋二)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
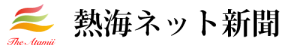





















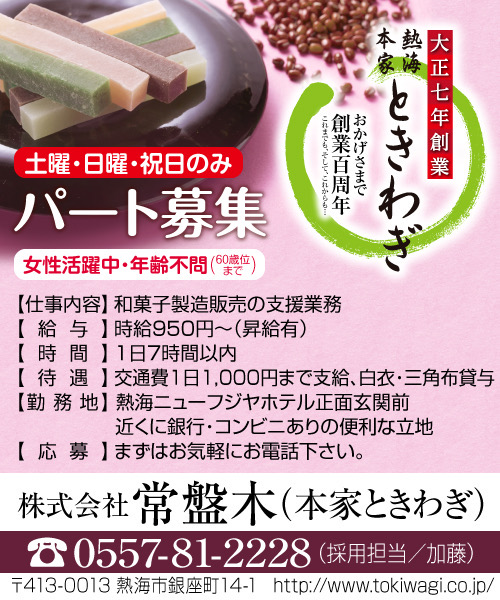
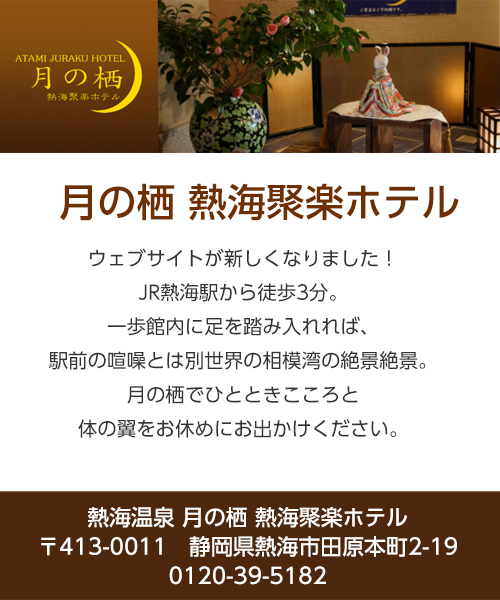
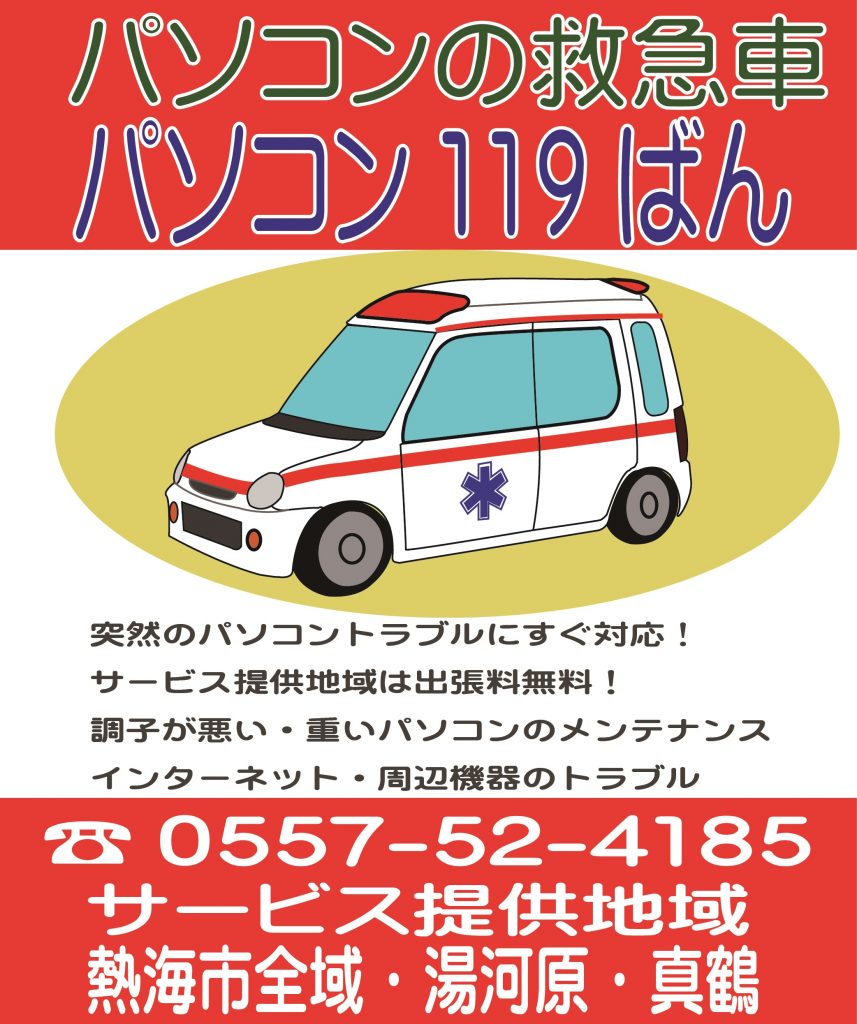
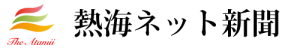
この記事へのコメントはありません。