
呼び物の湯くみ道中パレードは3日午後1時、熱海笛伶会が演奏する熱海ばやしが鳴り響く中、熱海駅前を出発。江戸時代、28里(約109キロ)離れた江戸城に90度の源泉をわずか15時間で献上したという故事に倣って「湯くみ道中」を再現した。本丸に着いた時分にはちょうどいい湯加減になり、将軍はそのまま入浴したという。
巫女(みこ)に扮したミス熱海が献湯の手桶、熱海芸妓衆が神社に奉納する湯の入った白磁の瓶子(へいし)をそれぞれ持ち、湯前神社神輿保存会の女性メンバーが「御本丸御用」の札を立てた献湯神輿を担いでパレードした。献湯を護衛するように裃姿の道中奉行に扮した佐藤元昭奉賛会会長、藤曲敬宏県議や市議が続き、斉藤栄市長らとともに平和通り、咲見町、銀座通りを経て湯前神社に運んだ。
◇湯くみ道中 徳川家康が熱海で湯治したのに倣って、4代将軍家綱は熱海・大湯の温泉が入った樽に「御本丸御用」の旗をたて、武士の護衛の下に江戸城まで運ばせた。その後、船輸送に代わったが、最も盛んだった8代将軍吉宗の時代には9年間に3640樽を献湯したと伝えられている。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。




























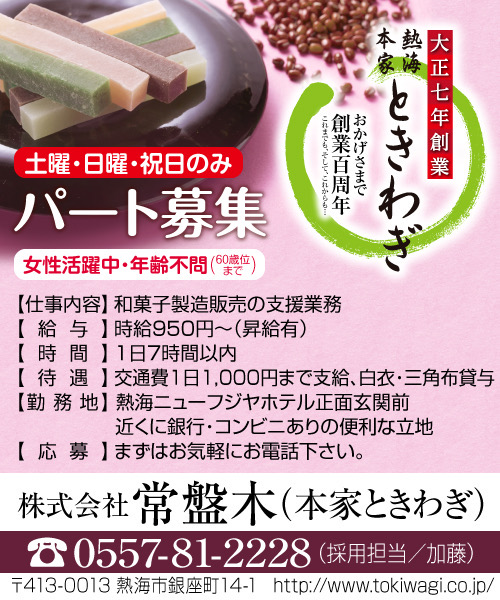
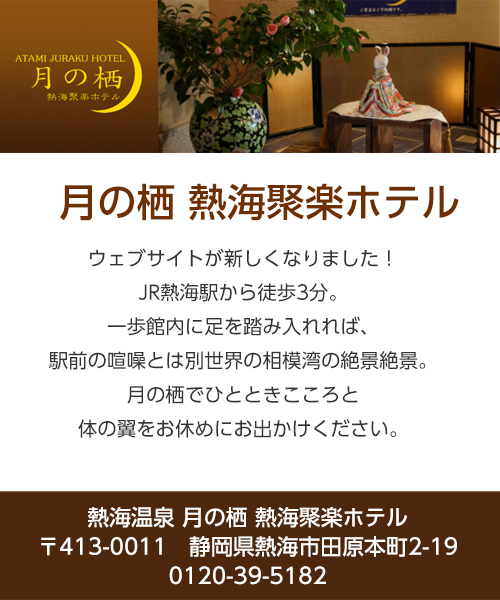
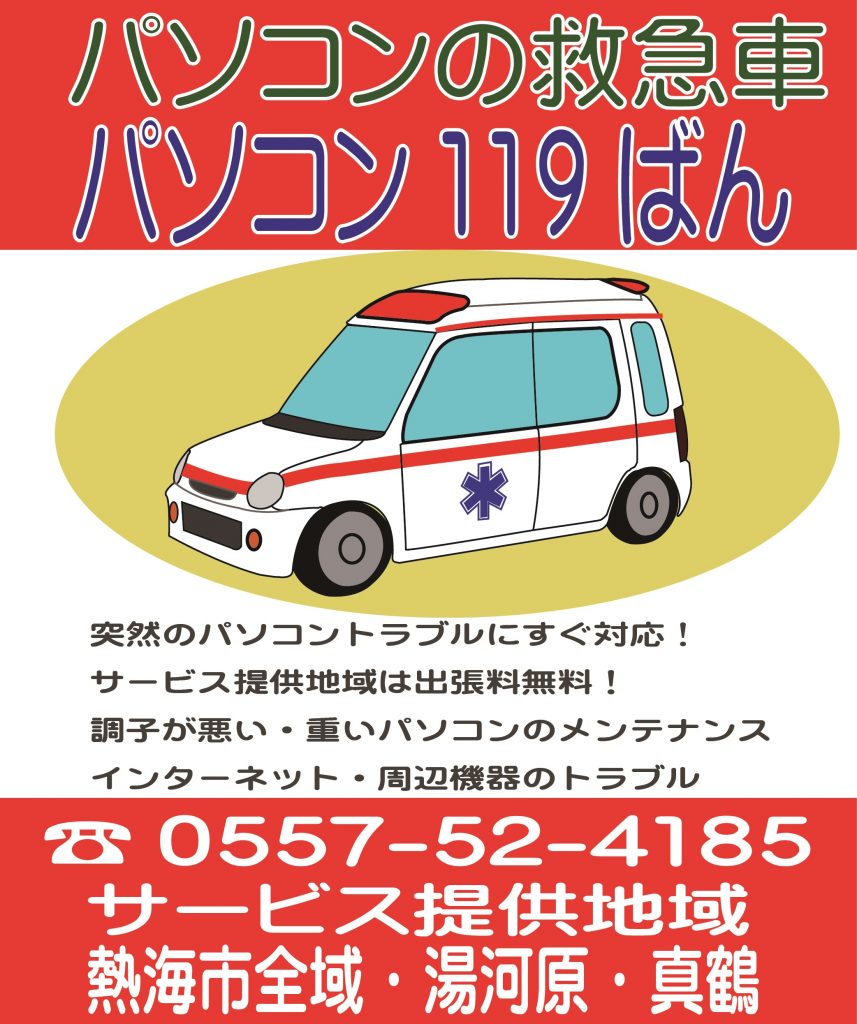
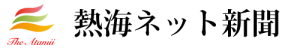
この記事へのコメントはありません。