
伊豆山神社(原口尚文宮司)が所蔵する「銅造伊豆山権現立像(いずさんごんげんりゅうぞう)」の保存修復が終わり、4月1日、同神社にある熱海市立郷土資料館で展示が再開された。この像は、鎌倉時代にさかのぼる伊豆山権現の優秀な作品とされながら、全身に広がる腐食が著しく、とりわけ面相部を覆う分厚い錆(さび)が像容の正確な把握を困難にしていた。このため、2カ年にわたり、奈良国立博物館と奈良文化財研究所が保存修理を実施した。
像表面の錆を落としたところ下層から造立当初の鍍金(ときん)が残る威厳ある顔立ちがよみがえった。像は立烏帽子(えぼし)を被り、顎鬚を(あごひげ)のほうと指貫(さしぬき)を着け、その上に袈裟(けさ)を懸ける独特の服装から、伊豆山権現の一遺品と考えられる。同研究所の年輪年代調査では1145年という原木伐採の上限年代が示された。像容と制作年代が分かったことから、文科省が国の重要文化財に指定する可能性が高いという。
熱海市に戻るのに先立ち、奈良国立博物館では2月6日から3月14日まで特別展「伊豆山神社の歴史と美術」を開催し、修復した「銅造伊豆山権現立像」に加えて同神社が所蔵する重要文化財「男神(だんしん)立像」「走湯権現当峯辺路本縁起集(そうとうごんげんとうぶへじほんえんぎしゅう)」「紺紙金字般若心経(こんしきんじはんにゃしんきょう)」「剣(けん)」をはじめ、「男神立像・女神(じょしん)立像」「法華曼荼羅(ほっけまんだら)」「阿弥陀如来坐像(あみだにょらいざぞう)」「扁額(へんがく)」「走湯山秘訣絵巻(そうとうざんひけつえまき)」「経筒(きょうづつ)など26点を展示し、伊豆山神社の歴史と信仰を紹介した。
熱海市はこの期間を利用して3月末までの2カ月余り休館し、展示ケースの布張りの張替修繕などを行い、この日リニューアル開館を迎えた。
保存修理後
保存修理前
◆熱海市立伊豆山郷土資料館 1981年創立、中島博館長(写真)。銅造伊豆山権現像をはじめ、県の重要文化財の銅造走湯権現立像や木造阿弥陀如来、木造男神立像・女神立像、扁額「伊豆山大権現」、経筒、走湯山秘訣絵巻などの伊豆山神社の所蔵品や伊豆山地区に代々伝わる郷土資料20点を展示。9:00~16:00.水曜休。大人150円。
◆伊豆山神社 伊豆権現、走湯権現とも呼ばれ、平治の乱で伊豆国に流された源頼朝(1147~99)が平氏打倒の兵を挙げる際、挙兵を後援し鎌倉幕府樹立へと導いた。東国の守護神として絶大な信仰を集め、歴代将軍や幕府要人は伊豆山神社と箱根神社に参詣する「二所詣」を重ねた。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
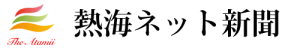






















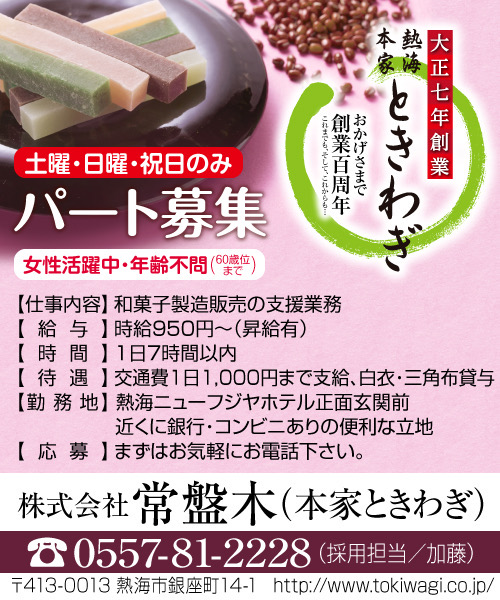
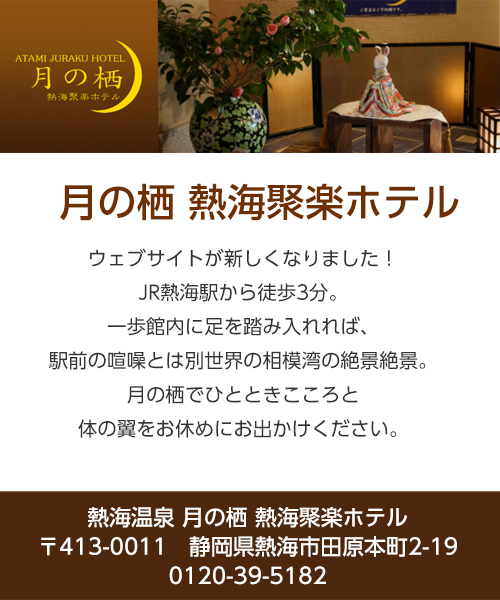
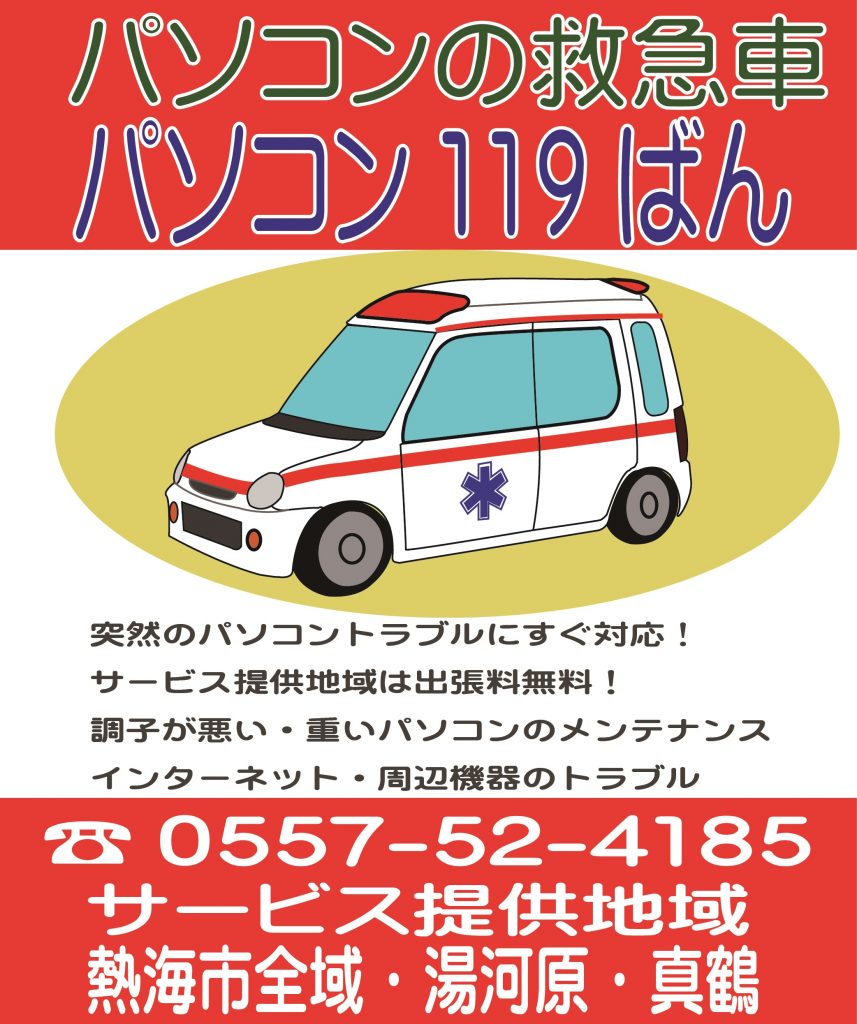
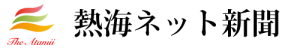
この記事へのコメントはありません。