
街歩きの名人タモリさんがブラブラ歩きながら知られざる街の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ・熱海編」が16日夜、NHK総合テレビで放送された。
今回のテーマは「人気温泉地・熱海を支えたものは?」。タモリさんは桑田真帆アナとともに、江戸時代・明治時代の古地図を手に熱海各所を回り、独自の視点で江戸時代以前は、小さな漁村にすぎなかった熱海が巨大な観光都市となりえた歴史のナゾを解き明かした。
熱海人気のきっかけを作ったのは、徳川家ご用達の温泉。家康公が湯治に訪れたことで歴代の将軍は熱海の大湯からくんだ温泉をたるにつめて江戸城に運ばせるようになった。8代将軍吉宗は9年間に3643たるを運ばせたという。
これで熱海温泉のブランド力が高まり、当時の温泉番付けでは最高位の大関草津温泉(上野)、有馬温泉(摂津)のさらに上位の行司役。葵の紋の熱海温泉をランク付けするのは不遜の極みというわけだ。
今回、初めて明らかになったのが江戸時代の熱海の人たちのお江戸での観光PR。タモリさんが熱海温泉誌作成委員会の松田法子実行委員長(京都府立大大学院専任講師)の案内で訪れたのは、江戸創業の老舗「古屋旅館」。当主の内田進さん(熱海商議所会頭)が「こんなものが出てきました」古い倉庫から持ち出したのは版木。タモリさんが刷ってみると意外な事実が分かった。作者は江戸時代を代表する僧侶「沢庵」。
その版木には「夜、昼4度、熱湯を噴出(間欠泉)する塩のいで湯」などと熱海温泉の説明や熱海で作った歌が刻まれており、タモリさんは「当時の熱海の人は沢庵和尚の歌を使って江戸で熱海の街を宣伝し、客を集めていたのでしょう、貴重なお宝」と読み解いた。これには内田さんも「なるほど、初めて知りました」。
さらに熱海の名声を高めたのは明治時代の華族、政治家、豪商たちの別荘ブーム。明治21年に天皇家の御用邸(現市役所の所)ができたことで、資産家たちの間で熱海に別荘を持つことがステータスとなり、大流行。富裕層の取り込みに成功した。
大正7年に始まった丹那トンネルの工事が昭和9年に完成すると今度は庶民に人気が広まった。東海道線が箱根回りから熱海経由になったことで関西方面からのアクセスが抜群に良くなり、年間乗客数が191万人に飛躍的増加。別荘地から熱海は庶民の観光地へ変化を遂げた。昭和36年には観光客が年間1000万人訪れるようになり、日本一の温泉地になった。
特筆すべきはタモリさんの慧(けい)眼。丹那トンネルの開通で一気に観光客が増えたことで起きたのが水不足の問題。温泉地熱海は地下を掘っても温泉しか出てこない。この危機を救ったのは、実は16年にわたり、計250万人ものトンネル工事者を苦しませた芦ノ湖3杯分もの丹那湧水。トンネル完成後、熱海は絶妙の高低差のある地形を利してこの湧水を水道に使い、水不足を救ったという。タモリさんの見識に今回も脱帽。
(編集主幹・松本洋二)
写真=NHK「ブラタモリ」より
コメント
この記事へのトラックバックはありません。


























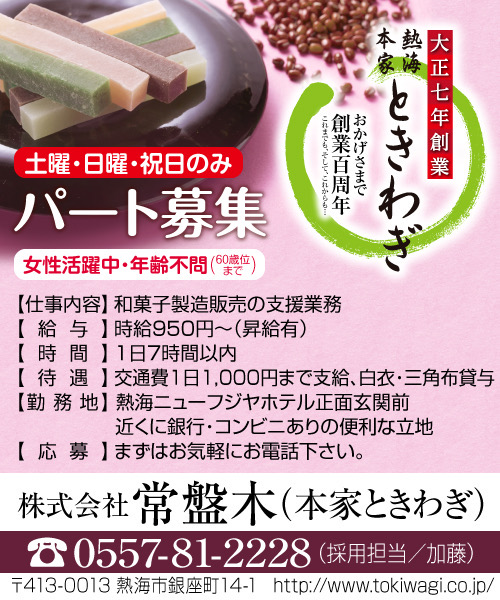
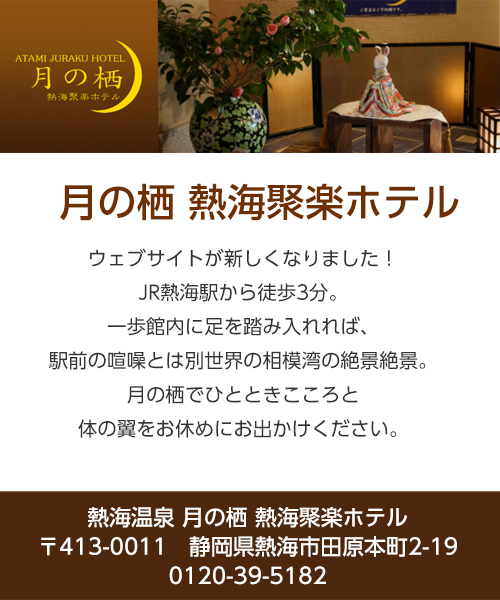
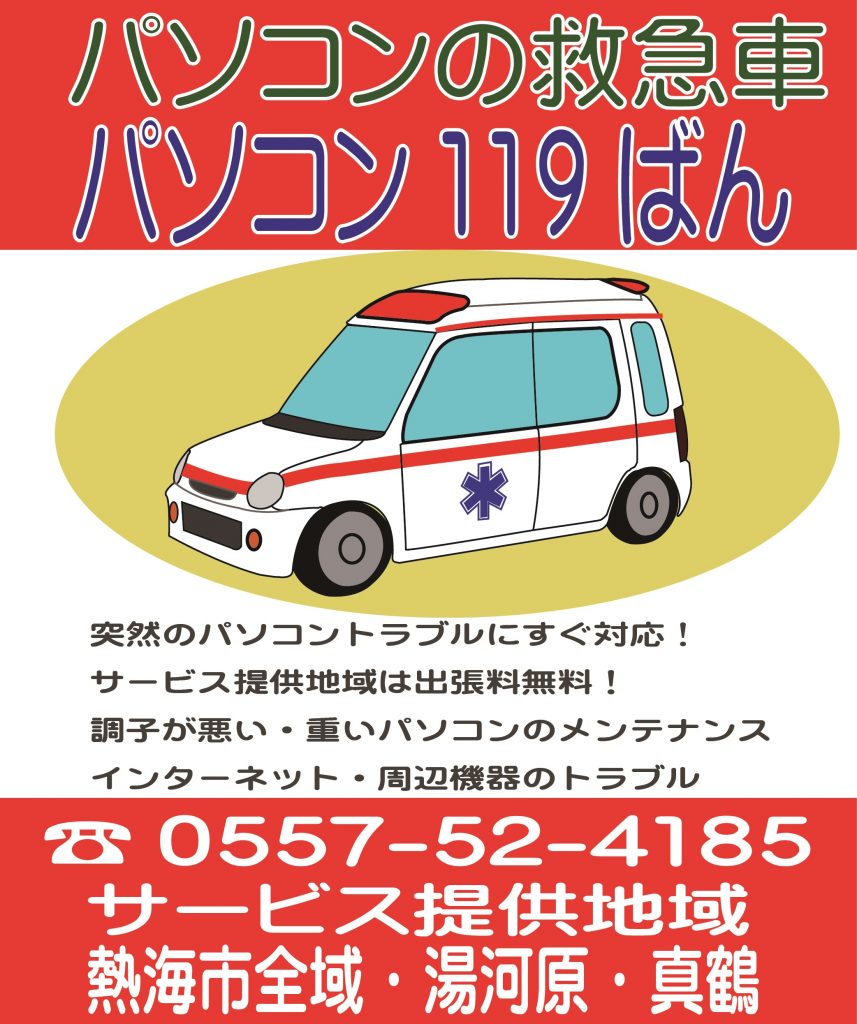
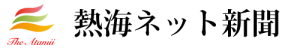
この記事へのコメントはありません。