
熱海市上多賀の「頼朝ライン」沿いの史跡公園「頼朝の一杯水」で4月24日、子育て延命地蔵尊大祭が斎行された。コロナ禍の影響で檀家が集まっての法要は3年ぶり。祠(ほこら)を管理する宝泉寺(加藤昭二総代長)の檀家代表8人が参列して御詠歌を奉詠したあと、高杉伸道住職が般若心経を読経し、源頼朝と八重姫の子・千鶴丸を供養した。
高杉住職は「ここ2年は本堂で自分がけで営んだが、今年は皆さんと一緒に供養できて嬉しい。お地蔵さん一体から始まった千鶴丸の供養は330年続いている。今後も続け、千鶴丸がこの世にいた証を次代に後世に伝えて行きたい」と述べた。
■841年前、頼朝、ほうほうのていで熱海へ
市議選の当選証書付与式と時間が重なり、参列できなかった檀家の稲村千尋市議によれば、子育て延命地蔵には、このような秘話が伝わるという。
父源義朝が1159年の平治の乱で敗れ、翌年14歳の頼朝は蛭ヶ小島(伊豆の国市)に流され、源氏再興の旗揚げをするまで約20年間過ごした。そんな折り、監視役の伊東祐親が伊東から京の大番役(京都の警護)に上っている間に娘の八重姫と恋仲になり、千鶴丸と名付けられた子供が生まれる。
1180年、3年ぶりに帰郷してこれを知った祐親は激怒。平清盛に知られれば、伊東家の滅亡の危機と恐れ、3歳の千鶴丸を松川の上流の滝に捨て、八重姫も幽閉の身に-。
頼朝も命をねらわれ、伊東を脱出して網代から船で上多賀の赤根崎に上陸。曽我裏を抜け、師と仰ぐ高僧覚淵(かくえん)の庇護をを求めて伊豆山権現(伊豆山神社)へ向かったが、険しい山道を登りつづけ、のどが渇ききった。途方に暮れて腰をおろし、刀の柄で大地を突くと、こんこんと清水が湧き出し、ぶじ伊豆山神社へ駆け込むことができたと…。
これが「頼朝の一杯水」と伝えられている。
■お地蔵さんの縁日にあたる4月24日に供養
同地蔵尊は、鎌倉幕府が開かれた約500年後の1693年、仏教修行僧の鉄意道心によって創建された。宝泉寺に道心が留まった際、村人からこの悲話を聞き、「頼朝の一杯水」のほとりに小さな祠を建て、自ら彫った地蔵の石像を安置し、供養したという。
現在の祠は、1961年に建て替えられたもので今は小公園となり、千鶴丸を祀(まつ)った新たな地蔵尊が安置されている。328年にわたり、地元の檀家によって、お地蔵さんの縁日にあたる4月24日に大祭を開き、供養を続けている。建て替えの際、初代地蔵は宝泉寺に移し、安置されている。
(熱海ネット新聞)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。























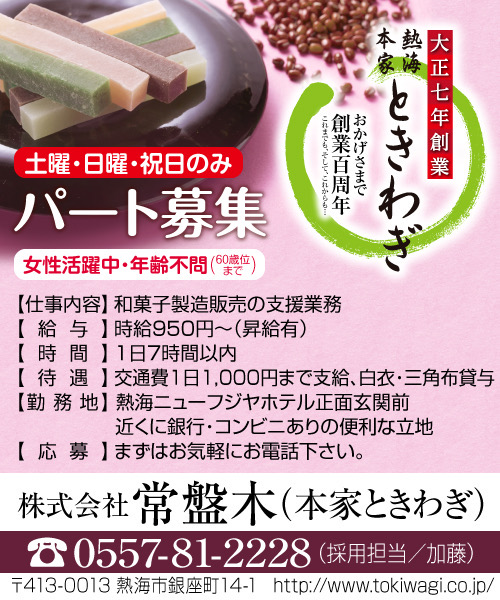
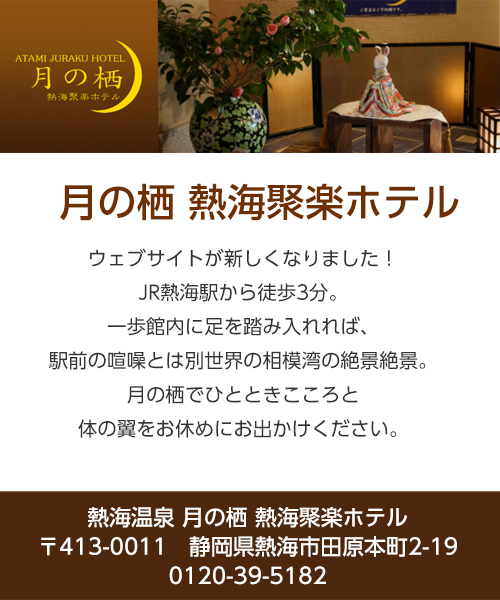
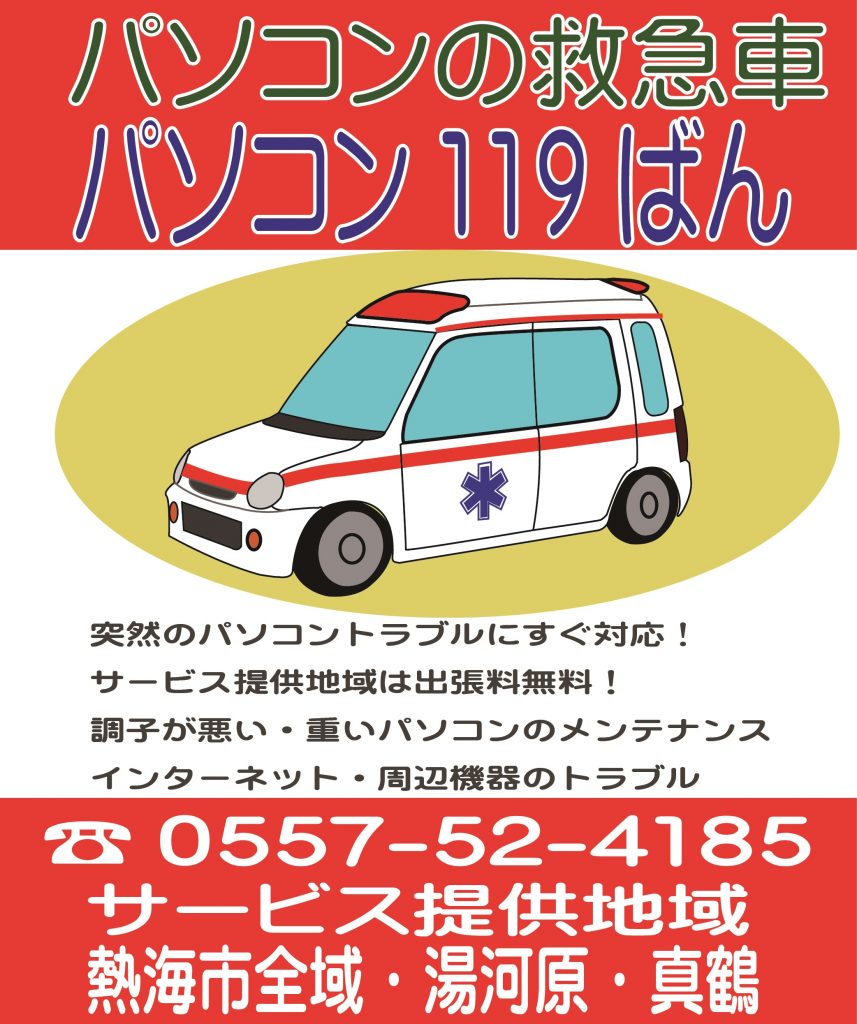
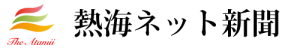
この記事へのコメントはありません。