
今年はカルガモの当たり年だった。5、6、7月に立て続けにカルガモの親子が熱海梅園で現れ、多くの市民が温かく成長を見守った。しかし、3組目の母子はこれまでのパターンだった初川下流への”疎開”がなく、「その後どうなった?」という問い合わせが数件あった。続報を掲載しなかったのは、この1カ月間に数奇なドラマがあったからである。
振り返れば、最初のカルガモ一家は母親が11羽の子をふ化させた。しかし、カラスの襲撃を受け、ほうぼうの体で初川の下流に疎開した。それでも外敵から守り切れず、3羽まで数を減らして巣立っていった。2組目はもっと悲惨。9羽いたヒナは初川下流に疎開したときには4羽に。外敵に襲われたのか、海に流されたのかは定かではないが、1羽、1羽と減り続け、結果は全滅。母親は単身で熱海を去った。
さて、7月初旬に現れた3組目のカルガモファミリーである。この母ガモを見ていると身につまされるというか、自然界の知恵、学習能力の高さを思い知らされる。先の2組の母ガモが子供たちを守れなかったのは、ヒナの数が多過ぎて外敵から守れなかった。そう判断したのだろう。そこで母ガモは10個産んだ卵のうち、これぞと見込んだ2個の卵だけをふ化させ、残りの8個は無視する奇策にでた。「どちらか1羽にだけでもDNAを伝えたい」と。しかし、まもなく1羽が外敵に襲われ、残るは1羽。これは非常事態と”マンツーマン”の子育てが始まったのだが、それもものかわ、数日後にその子も失った。
その後の、母親の行動が興味深い。いったんは、当初の作戦を変更して8個の卵の元に戻り、抱き始めた。しかし、失った2羽の子供たちの悲劇がトラウマになったのか、ドライにも抱卵するのをやめ、子育てを放棄。先月末に熱海梅園を飛び去った。
これが、今回のカルガモ母子が初川下流に姿を見せなかった真実と顛末。そこから透けて見えるのは、言葉では説明しきれないカルガモたちの情報伝達と学習能力の高さ。自然界から教えられることは多い。
(熱海梅園取材班)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。



















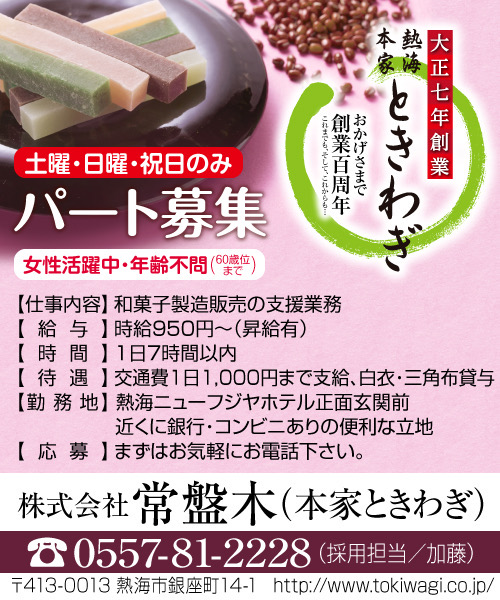
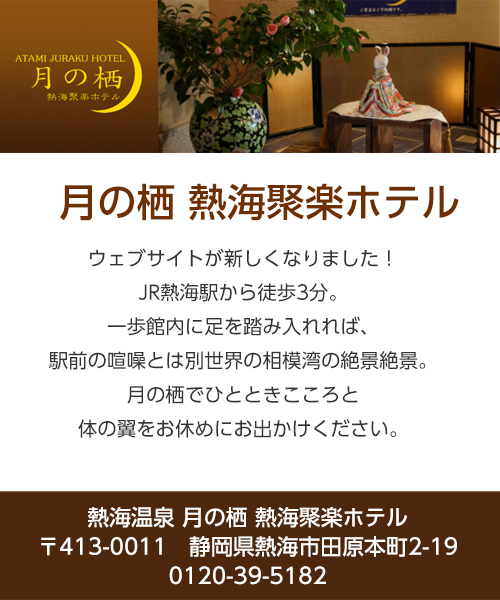
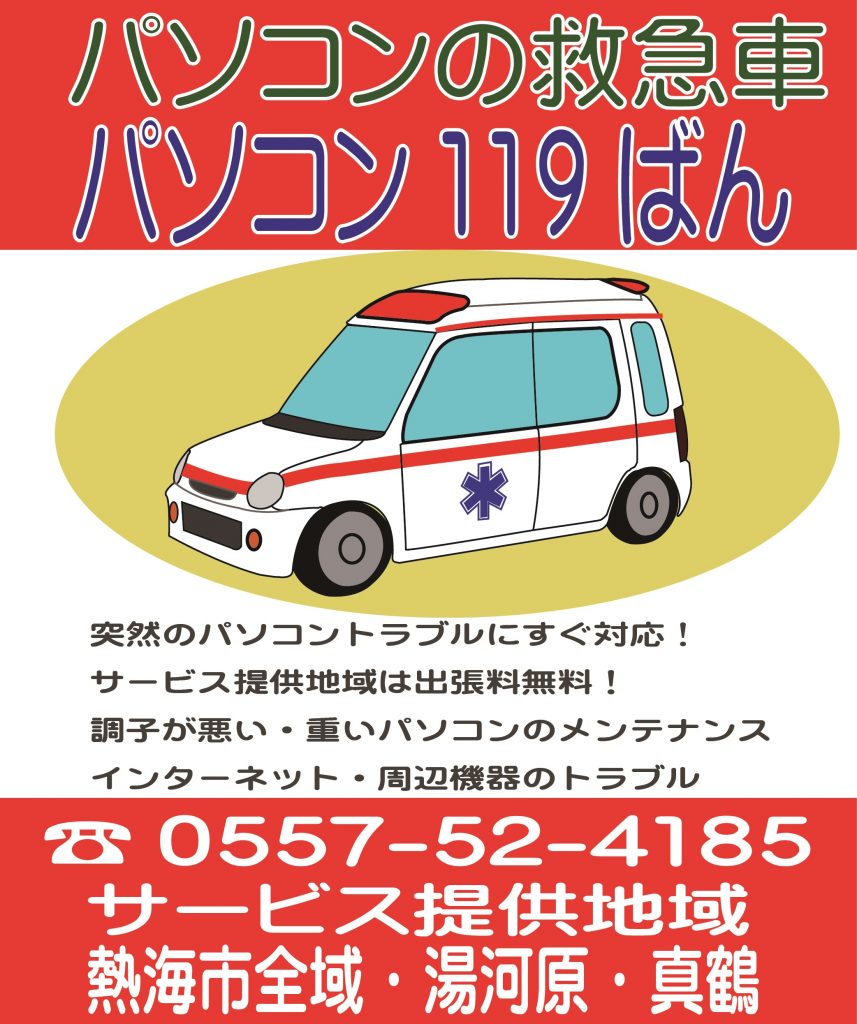
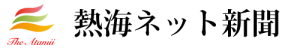
この記事へのコメントはありません。