
熱海市のお盆の伝統行事「百八体流灯祭」(多賀観光協会主催)が8月16日夜、規模を大幅に縮小して開かれた。例年は上多賀の長浜海水浴場から中野の小山臨海公園までの約3000メートルに290基のかがり火を灯して先祖の精霊を送るが、今年は新型コロナウイルス拡大防止のため、長浜海水浴場の砂浜だけで行い、数も20基に減らして実施した。
「百八体流灯祭」は戦前まで300年続いた仏事。山から切り出した燃木(もしき)を井桁(いげた)に組み上げ、赤根、白石地区から中野海岸までの区間に2間(約3・6メートル)置きに並べ、僧侶の読経とともに一斉に火を灯して先祖の霊をなぐさめたという。
同協会が昭和30年代にお盆の行事として復活させ、現在は長浜海水浴場から中野海岸までの国道135号沿いに290基のかがり火を設置。地域住民が分担して火をともす。眺めの良い場所には毎年大勢の見物人が集まることから、その密集と行事の担い手の密接を避けるため、異例の形で開催した。
(熱海ネット新聞)
■日本一 京都や箱根など大規模な「大文字」の送り火はあるが、「一文字」では多賀の送り火は日本最大級。例年は、多賀湾が橙(だいだい)色に染まり、ゆらめく炎が幻想的-。



コメント
この記事へのトラックバックはありません。

















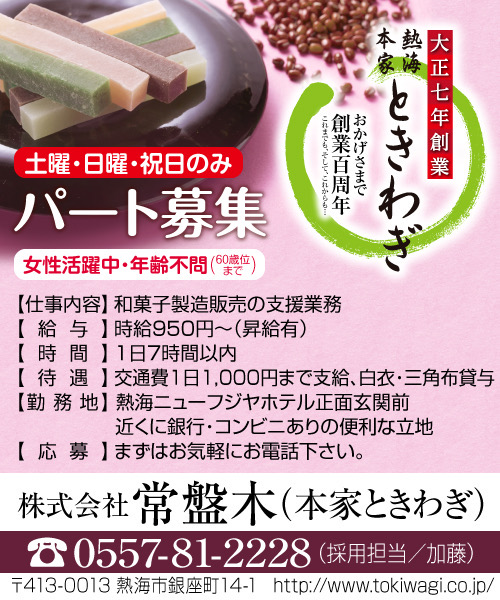
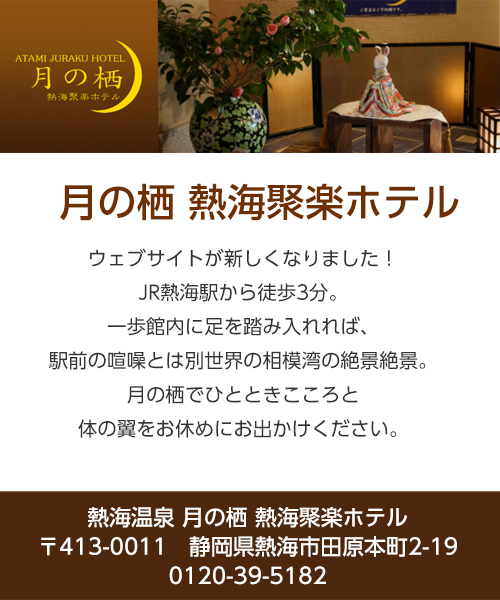
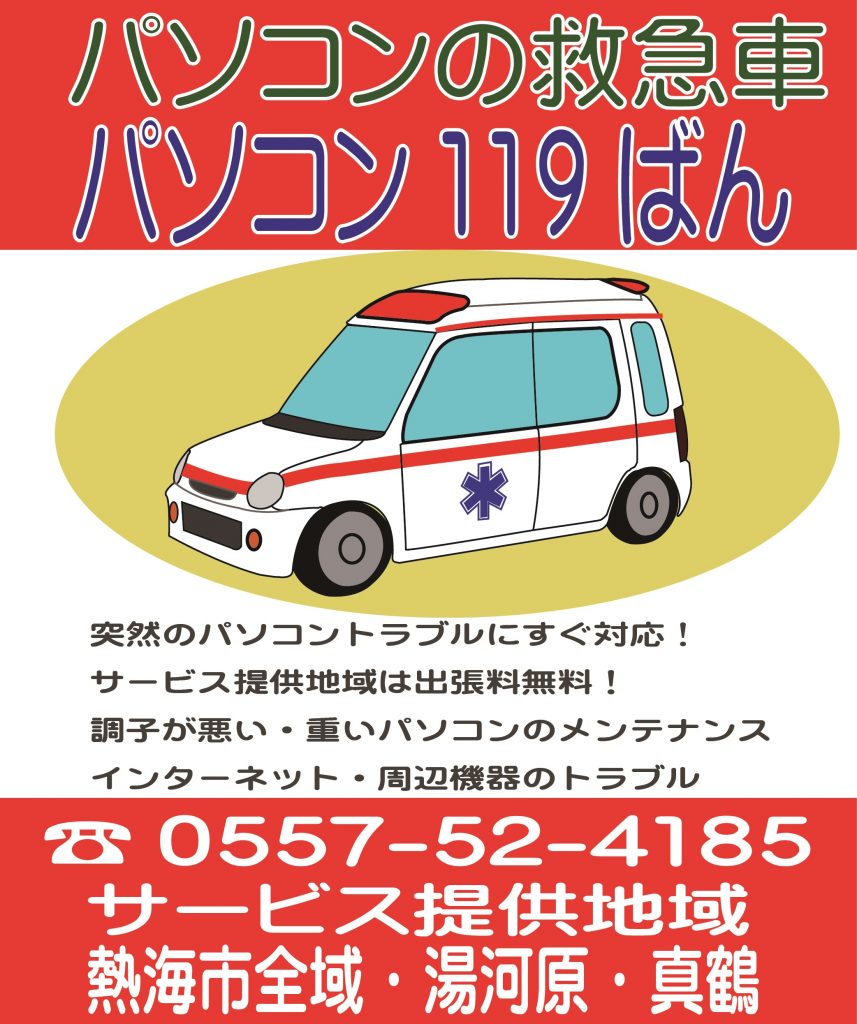
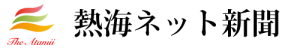
この記事へのコメントはありません。