
熱海駅のランドマーク的存在だった蒸気機関車「熱海軽便7号機」が12日夜、間欠泉の隣に鎮座していた駅前広場を離れ、熱海鉄道同好会のみなさんをはじめ、市民が見守る中、約80m離れた仲見世通り入り口付近に引っ越した。
熱海駅前の整備事業の一環だそうで、機関車周辺の整備は年内に完成する。
小田原から熱海への道は地形が険しく、丹那トンネルができるまで東海道本線は今の御殿場線(国府津-沼津)を走っていた。明治40年から大正12年にかけて熱海~小田原間の25キロを2時間40分かけて白煙を上げていたのがこの蒸気機関車だ。長さ3.36m、高さ2.14m、幅1.39mの初期のミニSL。熱海駅前に展示してあるのはその7号機で昭和50年12月から置かれていた。
それまで熱海の来遊客は皇族や政界の大物など一部の特権階級に限られていたが、この鉄道の開通で庶民へと広がりを見せ、大湯を中心とした当時の市街地には坪内逍遙(文学者)や内田信哉(実業家・政治家)などが次々に別荘を構えた。それに伴って熱海の市街地も拡大していったという。
その意味では「熱海軽便」は「お宮の松」に勝るとも劣らない功労者。「まちおこし」のために再整備して市街を走らせれば、新たな誘客コンテンツになるのでは…。ひっそりとした夕刻の銀座通りを歩いていると、大湯の方角からゆっくり、ゆったり発進する蒸気音が聞こえてきた。(編集主幹)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。



















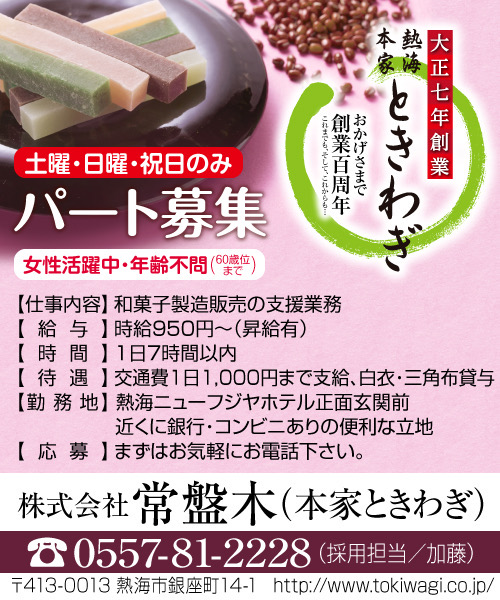
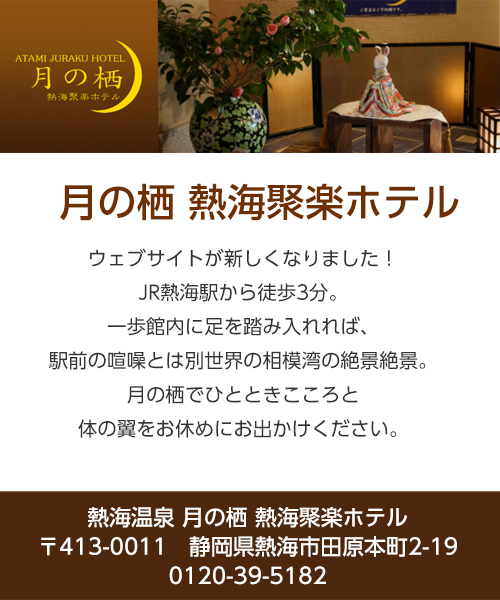
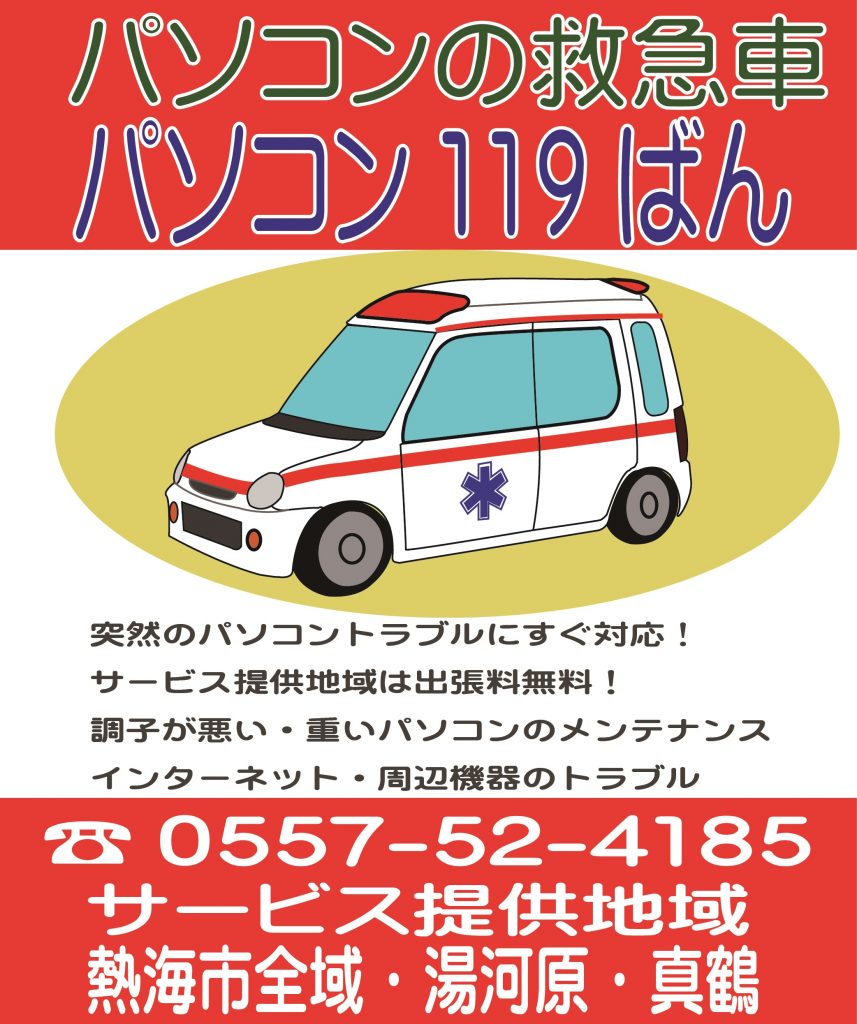
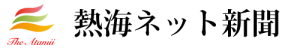
この記事へのコメントはありません。