
日本を代表する花街、熱海の「熱海をどり」が28日、熱海芸妓見番歌舞練場で始まった。27回目の今年は常盤津「千代(ちよ)の友鶴(ともづる)」と端唄俗曲「おんな艶姿雨模様(あですがたあめもよう)」を披露。立方18人、地方8人による艶(あで)やかな舞台が会場を盛り上げた。29日も午前と午後に開催される。
常盤津「千代(ちよ)の友鶴(ともづる)」は、1860年代(江戸末期)に作曲されたもので、別名「広尾八景」。東京・広尾周辺の景色を詠んだ曲だが、今回の熱海をどりでは王朝風(平安時代)の雅な踊りに仕上げている。

「おんな艶姿雨模様(あですがたあめもよう)」は、雨をテーマに五景で構成。花街では「雨は客をふりこむ」とされ、縁起がいいものとされる。第一景は傘を使って「雨の深川」「三太郎ぎつね」「夕立や田を」「小万しぐれ」が順に披露され、踊りで四季の雨を表現した。
琴千代(左)、初文

第二景「玉の井の女たち」では、「薄墨(傘を持つ女)」「青いガス燈(たばこを持つ女)」「びんのほつれ(とっくりをだく女)」「芝で生まれて(猫をだく女)」「柳々(あやとりの女たち)」が披露され、花街の女性たちの雨の日の微妙な心の揺れを巧みに表現した。
第三景では「おかる」「定九郎」「猪の女たち」で芝居の雨を創り出した。雨の彩り、艶やかさの中の雨などで舞台を彩った。
第四景の「雨の深川」に続いて、出演者全員によるフィナーレの「三下(さんさ)がり」を終えると、西川千鶴子組合長(松千代)が「九州のほうでは大変な災害に見舞われており、皆々様に心よりお見舞い舞い申し上げます。このようなときではございますが、恒例によりお手を拝借」とあいさつし、全員で三本締めを響かせた。

◆熱海をどり 熱海芸妓見番の大改修(平成2年)を記念してスタート。日本一の規模を誇る熱海芸妓衆が年に2日(4月28、29日)開催する熱海のGWの看板イベント。主催熱海芸妓置屋連合組合
コメント
この記事へのトラックバックはありません。



































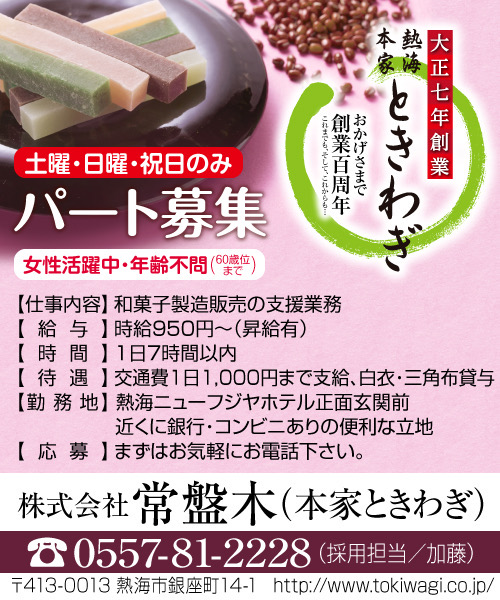
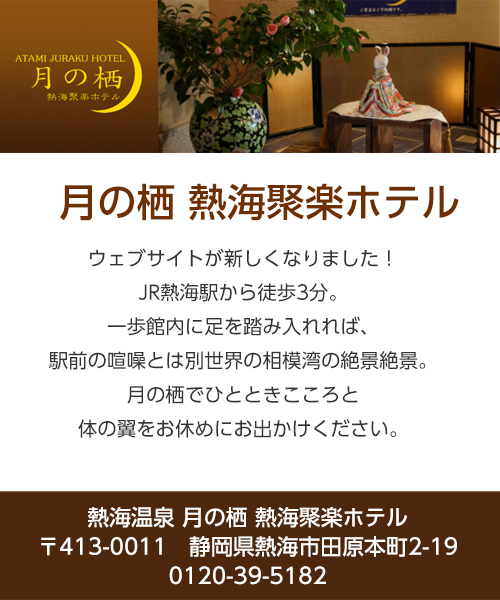
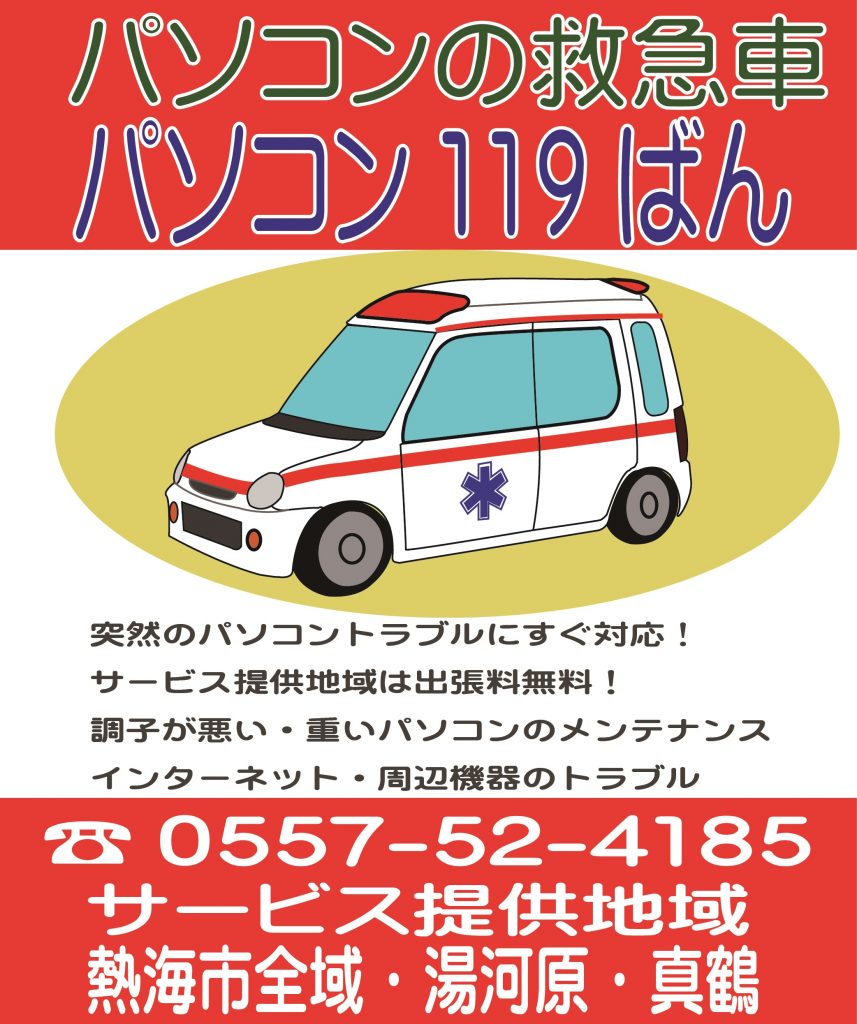
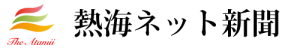
この記事へのコメントはありません。