
お酒を味わいながらMOA美術館の展示作品を学ぶ「ほろ酔い講座」が11月5日夜、熱海市銀座町のゲストハウス「マルヤ」で開かれた。同美術館の特別展覧会に合わせて催される人気イベント。通産16回目となる今回は、10月27日から始まった特別企画展「武者小路千家・千宗屋のキュレーション・茶の湯の美」(~12月10日)がテーマ。同美術館広報の泉山茂生さんが千利休からおよそ400年続く伝統の茶の湯を分かり易く解説した。
今回もお酒コーディネーターの石和宏深さん(石和酒店)がとびっきりの”お供”をセレクト。食前酒にドライベルモット「ドラン」、メーンに英君・白菊純米吟醸、食後酒は正雪にごり「スパークリングSNOW」。同ハウス女将の豊田千穂さんとともに、参加者をもてなした。
■豊臣秀吉が黄金の茶室で用いた「天目茶碗と茶入」同時公開
泉山さんの今展覧会のイチオシは豊臣秀吉の「黄金の茶室」(復元)に展示される「黄金の天目茶碗(個人蔵)と茶入(MOA美術館所蔵)」。秀吉が実際に黄金の茶室で用いたと伝えられるもので、大坂城が落城した大坂夏の陣(1615年)の際、徳川家康が江戸に運ぶ途中、名古屋城に留め置かれたままになっていた。その後、家康の9男、義直の生母・お亀の方から家老竹腰家に下賜(かし)。時がたち、三井物産を創業した益田孝氏(茶人・益田鈍翁)が手中に収めたが、その後、天目茶碗の行方がわからなくなっていた。このほど所有者が分かり、二つの同時公開はおよそ半世紀ぶりという。
平安時代に中国から伝わった豪華絢爛のお茶ワールドから、精神性重視の室町時代、織田信長、秀吉の”武士の恩賞”、家康のうっかり…千利休や古田織部、小堀遠州も登場し、利休には熱海で湯治したことを伝える書状もあるという。
ほろ酔い講座は、ゆるーく2時間半。次回が楽しみだ。
(熱海ネット新聞・松本洋二)
写真=黄金の天目茶碗(個人蔵)と茶入(MOA美術館所蔵)はMOA美術館より
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
































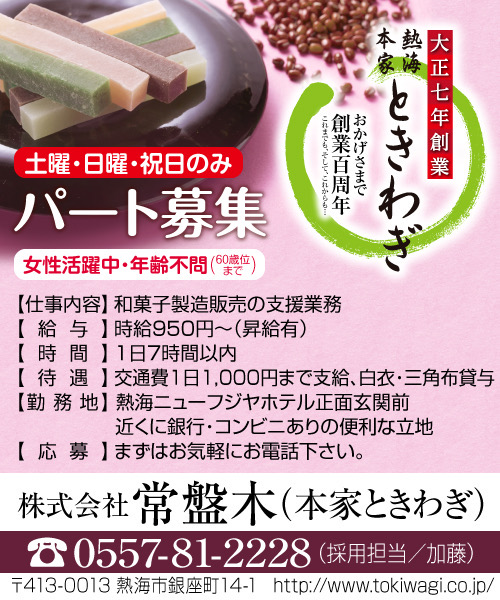
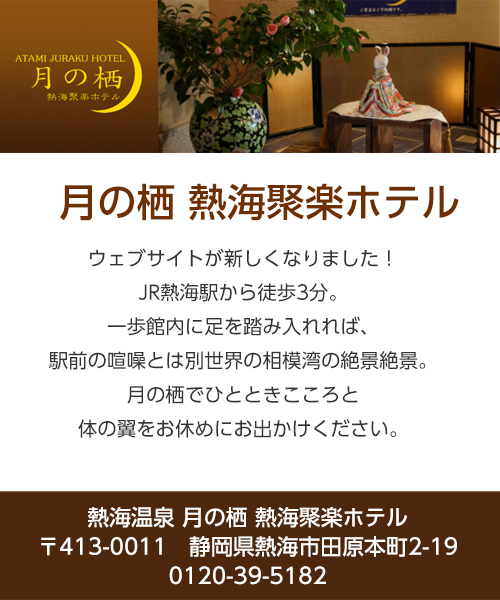
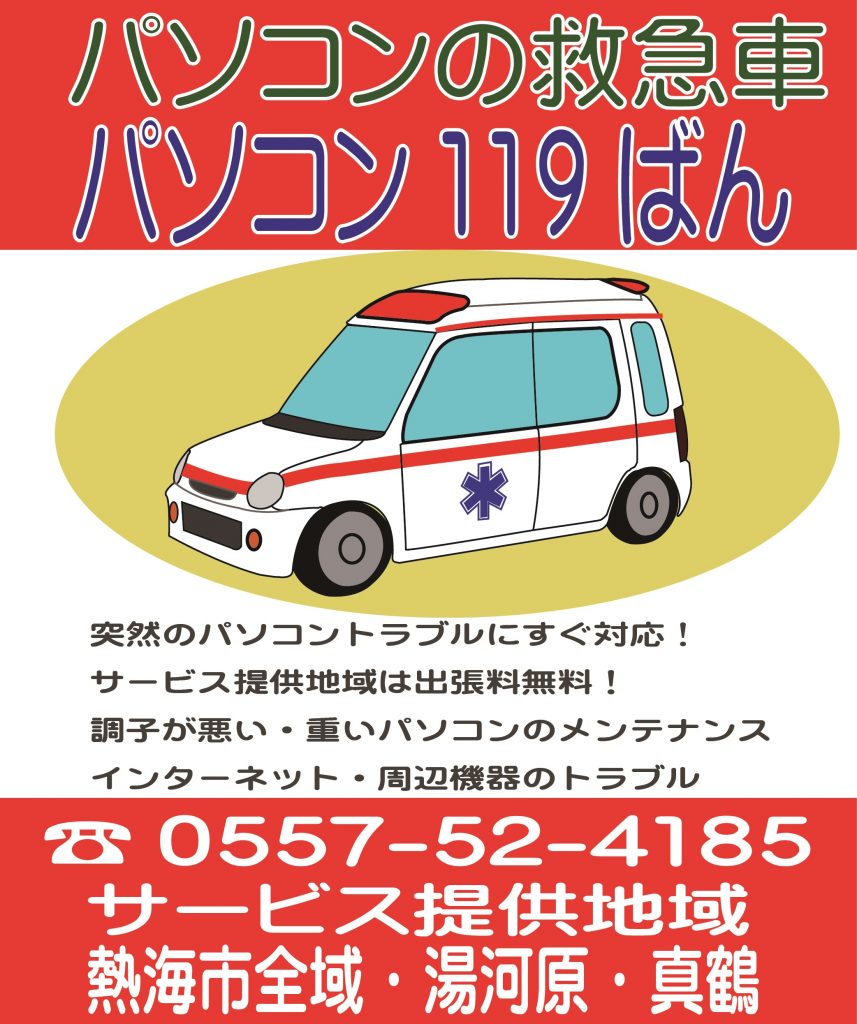
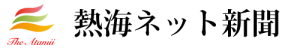
この記事へのコメントはありません。